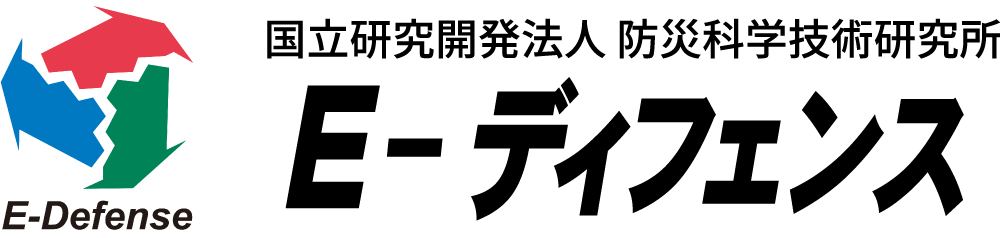E-ディフェンスとはAbout us
- ホーム
- E-ディフェンスとは
- センター長挨拶
センター長挨拶
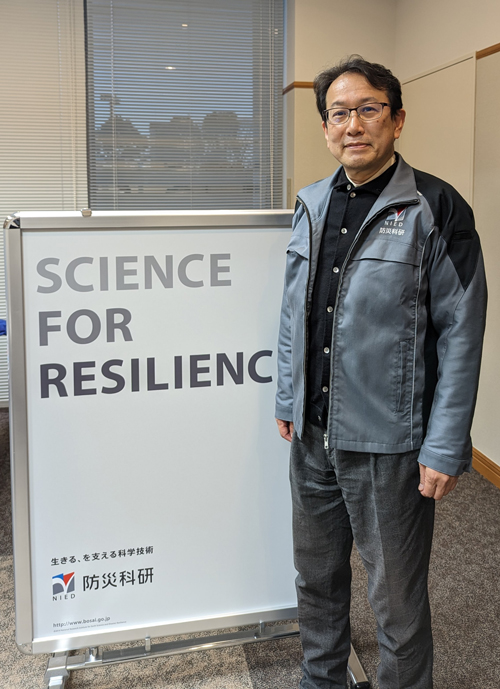
中埜 良昭
1995年兵庫県南部地震を契機に建設されたE-ディフェンスは2005年の運用開始以降、 120件を超す振動実験を実施してきました。その初期においては構造物の破壊過程の解明や耐震性能評価に主眼を置いた実験を、その後は単に崩壊しないだけでなく、地震後の機能維持能力や崩壊に対する余裕度の評価とその向上、積極的に余裕度を付与するための応答制御技術、また構造体だけでなく非構造部材を含む崩壊余裕度評価に着目した実験を実施し、さらにそれらを解析的に再現するための数値シミュレーション技術(数値震動台と呼びます)の開発を進めてきました。
これらの一連の研究開発では、主として構造物単体(single structure)を対象に一回の地震(single event)に対する応答に重点を置いてきたと言ってよいでしょう。すなわち「個」を極める研究開発に主軸を置いてきたわけです。その重要性は不易のものでありますが、一方で南海トラフの巨大地震や首都直下地震のような広域・甚大な被害が危惧される災害時に日本がいち早く社会経済活動を復活・継続できることは極めて重要であり、そのためには様々な「構造物群」で構成される都市のレジリエンスを高めることが肝要であることは論を俟ちません。
そこで本格的に「都市」を対象として、そのレジリエンス強化に直結する研究開発を目指し、都市空間内の構造物群(すなわち都市、multiple structures)へ、また都市を対象とすれば発災直後から復興に至る中長期間に当然経験するであろう複数回の地震(multiple events)へと対象を広げ、現在はまだ顕在化していない未然の課題や現象の解明、さらに将来のリスクを予測することで予防や早期対応に寄与することを目標に掲げ、それらのための技術群の開発を現在進めています。
また物理的な破壊実験に加え、数値シミュレーションによるリスク予測技術の高度化が今後ますます重要となるでしょう。とりわけ「都市」への展開を考えた場合、都市をモデル化したサイバー空間でのシミュレーション技術への展開が不可欠です。破壊実験と両輪をなす数値震動台では、シミュレーション技術開発の一丁目一番地である構造物の高精度な挙動再現技術だけでなく、デジタル・ツイン空間における都市のハイサイクル・シミュレーション技術の実用化も目指します。また実験的研究とシミュレーション技術の高度化が双方向に連携しつつ発展するためには高品質なデータを届けたい人に確実に提供できるようなサービスと環境整備にも注力する必要があります。
E-ディフェンスではこれらの取り組みにより具体的な成果が創出され、都市のレジリエンス高度化に寄与する技術・知見が充実してゆくよう、研究開発に取り組んでゆきたいと考えています。